本展では、とりわけ多くの画家や版画家たちがブルターニュを目指した19世紀後半から20世紀はじめに着目し、この地の自然や史跡、風俗、歴史などをモティーフとした作品を展覧することで、それぞれの作家がこの「異郷」に何を求め、見出したのかを探ります。また明治後期から大正期にかけて渡仏し、この地に足を伸ばした日本の画家たちの作品と足跡にも光をあてる、これまでにない試みとなります。

憧憬のブルターニュ

ごあいさつ
フランスの最北西端、大西洋に突き出た半島を核とするブルターニュ地方は、芸術家と縁の深い土地です。ケルト人を祖にもち、16世紀前半まで独立国であったこの最果ての地は、隣国のイギリスとフランスに翻弄されながらも独自の歴史と文化を紡ぎ、フランスの一部となったのちも固有の言語「ブルトン(ブレイス)語」を守りつづけました。またこの地には、断崖の連なる海岸線や岩で覆われた荒野、内陸部の深い森をはじめとする豊かな自然とともに、古代の巨石遺構や中近世の宗教遺物が数多く残されています。人々の篤い信仰心や、地域色に富む素朴な生活様式も長らく保たれてきました。このように特徴的な自然と歴史文化を擁するフランスの内なる「異郷」は、19世紀以降、新たな画題を求める画家たちを惹きつけて病みませんでした。 本展では、とりわけ多くの画家や版画家たちがブルターニュを目指した19世紀後半から20世紀はじめに着目し、この地の自然や史跡、風俗、歴史などをモティーフとした作品を展覧することで、それぞれの作家がこの「異郷」に何を求め、見出したのかを探ります。また明治後期から大正期にかけて渡仏し、この地に足を伸ばした日本の画家たちの作品と足跡にも光をあてる、これまでにない試みとなります。 国内およそ30ヶ所の所蔵先、さらに海外2館から集められた約160点の作品にくわえ、多岐にわたる関連資料も展示されるこの機会に、皆さんも画家のまなざしを借りてブルターニュの各地をめぐり、芸術を育むその奥深い風土を体感していただければ幸いです。 最後になりましたが、本展開催にあたり、貴重な作品をご出品いただいた美術館並びにご所蔵者の皆様、調査にご協力いただいた皆様、ご支援、ご協賛、ご協力を賜りました関係各位に心よりお礼申し上げます。 主催者

憧憬のブルターニュ
国立西洋美術館
2023.3.18 SAT 6.11 SUN


ご挨拶
フランス北西部ブルターニュのカンペール市中心に位置するカンペール美術館は、今から約150年前の1872年に開館した歴史ある美術館です。所蔵作品には、ルネサンスからロココ時代に至るオールドマスターによる絵画のほか、ポン=タヴァン派などとともに、ブルターニュ地方の自然や風俗などを描いたフランス随一の充実度を誇る作品群があります。 ブルターニュ地方は豊かな自然とケルトの伝統を色濃く残す独自の文化を持ち、19世紀後半から20世紀はじめにかけて、この地に魅了され、足を運んだ多くの画家たちが、その自然や歴史、風俗を描き出しました。 本展ではカンペール美術館の所蔵品を中心とする60余点の絵画を通して、恩恵とも脅威ともなるブルターニュの自然、海と大地に暮らす人々の生活、同地特有の宗教儀礼「パルドン祭」に象徴される人々の深い信仰心や精神世界を幅広くご覧いただきます。あわせてサロンで活躍したアカデミスムの画家やポン=タヴァン派、それ以降の画家たちによる多様な絵画表現の展開もご紹介いたします。 本展が、みなさまにとって新しい発見となり、また、絵画を通じたブルターニュを巡る旅としてお楽しみいただければ幸いです。 本展開催にあたり、貴重な作品をご出品くださいました所蔵美術館、関係各機関に深く感謝申し上げます。 主催者
いざ、国立西洋美術館へ!



Ⅰ 見出されたブルターニュ:異郷への旅
Ⅰ−1.ブルターニュ・イメージの生成と流布

画家たちによるブルターニュ地方の再発見は、19世紀初めのロマン主義の時代まで遡ります。革命期を経て国民感情が高まるフランスにおいて、あらためて注目されたのが自国の自然や歴史的遺産の多様性でした。さらにイギリスではじまった地方の風景に美を探す旅、「ピクチャレスク・ツアー」の流行が追い風となり、画家たちは絵になる景観を求めてフランス北西端を目指すことになります。こうした動きは、各地方に残る自然や史跡を克明に描き出した挿絵本の出版も促し、見知らぬブルターニュに対する読者の好奇心を満たすと同時に旅心を誘いました。かたや文人たちがペンで描写するブルターニュの姿もまた人々の想像力を掻き立てるのでした。
19世紀半ばを過ぎるとブルターニュは近代的な観光旅行の時代を迎えます。1857年にパリと中心都市レンヌを結んだ鉄道は、1863年には半島先端部の主要都市カンペール、その2年後に軍港を擁するブレストへと伸延し、「最果ての地」との往来を格段に容易にしました。時間と心理的な距離の双方が短縮したこの時代、ブルターニュにまつわるイメージは増産され、そのステレオタイプ化も進みます。当時出版された版画集に現れる巨石遺跡や港の眺め、特異な風俗、あるいは世紀末の版画にしばしば見られるコワワ(頭飾り)と民族衣装を身につけた女性たち。異国情緒を前景化する図像の数々に、その例を見出せるでしょう。大衆向けの宣伝媒体である絵入りポスターはなおさら、ブルターニュ各地の特色をときに単純化し、現実からいくぶん乖離したイメージさえ流布させました。ここにはブルターニュのイメージが大量に生産・消費されるなかで、むしろその多様性が捨象されていくプロセスが垣間見えます。


1826年、ターナはロワール川を主題とする版画シリーズの制作を念頭に、初めてブルターニュの地を踏みます。10月1日にナントへ到着した彼は、2日間の滞在中に30点余りの鉛筆デッサンに街の景観を写しとりました。ロワール川とナントの街を望む本作は、そうしたデッサンにもとづき、更年アトリエで制作された水彩画の大作です。遠景にブッフェ塔やポワソヌリー橋を配した街並みを地詩的に表しつつ、前景では川辺に集う人々の多様な身振りや船の往来を描いて画面を画期づけています。水面に映し出される豊かな色彩や仄かな霞のごとき大気の表現には、この画家の鋭敏な感性がうかがえます。

背中の岩はが面白い!雰囲気ありますね


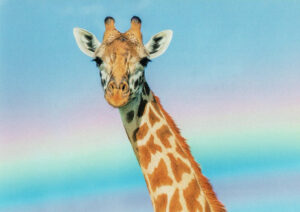
船ってこんなふうに接岸する?

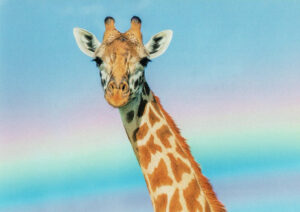
お祭りみたいだけど、道端に座っている人たちは?

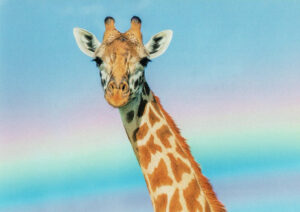
すごい荒々しい波。向こうの島に見えるのが墓でしょうか?

何かの事件?







Claude Monet クロード・モネ




1886年9月から11月にかけてのベリール滞在中、モネは「不気味な」岩々の連なる「コート・ソヴァージュ(荒れた海岸)」の風景を繰り返し描きました。その入江のひとつから巨大な洞窟を俯瞰する本作では、鮮やかな海原と陽光を浴びる岩肌が、きわめて色彩豊かな無数の筆触の並置により表されます。一方、別の作品においては、近接した視点から、灰色がかかった色彩と線条のストロークよって渦巻く嵐の海の動態が捉えられています。ベリールの変わりやすい天候と海面はモネを悩ませ、そのことがのちの「連作」の展開につながったとも考えられています。
Paul Gauguin ポール・ゴーガン

ゴッホとの短い共同生活の後、ゴーガンは1889年2月から再びブルターニュに移ります。ル・プールデュで秋頃に製作されたと考えられる本作には、断崖を背景に「素朴な農民な子どもたち」(1889年、ゴッホ宛書簡)が描かれています。寄り添って手を握り、怪訝そうな視線を投げかける少女たちの倹しい身なり、そしてむき出しの大きく逞しい足には、ゴーガンが彼らに見ると同時に、「自身の内にも宿る」と語っていた「野生」が象徴的に表されています。純色に近い色彩の対比、単純化された輪郭がモチーフを取り囲む画面は、印象派様式からの脱却と、「線合主義」理念の成熟を示しています。

最初のタヒチ滞在を経て1894年にボン=タヴェンを再訪したゴーガンは、タヒチで得た造形語法を用いて同地を描きました。ふたりの農婦には、彼の描くタヒチの女性たちの顔貌が投影されています。また、中景の茂みや草地、後景の民家に用いられた鮮やかな色合いには、画家が南洋で培った力強い色彩表現への痕跡が見出せます。ポン=タヴァンやル・プールデュではじまった「野生的なもの、原始的なもの」の探究が、文化的・地理的に遠く隔たったタヒチや、のちのマルキーズ諸島でのそれに接続し、移行していくさまがうかがえる作品です。

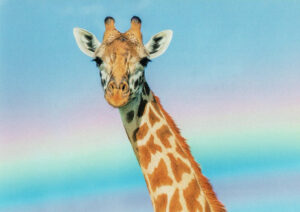
牛飼いと牛たちの姿が見えるね
木々の間から変わった形の岩が剥き出しになった寂しい風景。でも、広い空から爽やかな光と空気が感じられるよ

Paul Serusier ポール・セリュジェ


1893年と1894年に滞在したシャトーヌフ=デュ=フゥを気に入ったセリュジェは、1906年同地に居を構えて隠棲し、以降はブルターニュの歴史に取材した作品を多く残しました。本作には、中世のタペストリー(つづれ織)を思わせる装飾的な構図や人物造形により、15世紀末から16世紀初めにブルターニュ公園最後の女公にしてフランス王妃ともなったアンヌ・ド・ブルターニュと、若木の植えられた鉢を捧げて彼女に敬意を表す若い騎士の姿が描かれています。ケルトの樹木信仰や再生儀礼を踏まえたであろう若木の描写には、第一次対戦後のブルターニュの再生を願う画家の祈りが込められているのかもしれません。

Lucien Simon リュシアン・シモン

ブルターニュの婚礼やパルドン祭の縁日など、庶民の生活模様を自然主義的な態度で描いたシモンは、別荘で家族や友人と過ごすひと時も数多く描きとめました。本作は、シモン家の子供たちが別荘の庭で催した芝居を大人たちが見物する情景を捉えています。赤い天蓋の下で演奏や踊りを披露する子供たちと、それを暖かい眼差しで見つめる大人たち。画面と平行にそびえる別荘のファサードや生垣は、庭そのものを舞台であるかのように見せる書割りの役目を担い、それが家族の集いの親密な雰囲気を一層強めています。

本作はペロス=ギレックの北西部プルマナックで開催される、ヨットレースで有名な祝祭を描いたものです。画面手前の船にはドニの二人の息子の姿も認められ、また翌年ドニが再婚するエリザベツも赤いドレスに身を包み、紫陽花で飾られた戦場に座っています。この作品は、画家エドモン=フランソワ・アマン=ジャンや児島寅次郎が仲介するかたちで1921年に購入され、大原孫三郎のコレクションに入りました。本作に描かれる日本的なモティーフ(黄色い傘、提灯のような飾り、日本の国旗を思わせる旗)を、大原に対するドニの配慮と見る説もあります。

海難事故の絶えないブルターニュのサン島をを舞台に、島民たちが海で命を落とした漁夫を悼んでいます。立ち込める暗雲の下、横たわる遺体を囲んで悲しみにくれる老若男女。その背後に見えるのは、十字架の形をなすかに見える漁船のマストや帆桁。伝統的にキリストの死を哀悼する場面に用いられてきた図像に依拠することで、コッテは一漁師の死に壮重な聖性を与えたのでした。数年後に画家自ら制作した本作のレプリカは国に買い上げられ、現在はオルセー美術館に収蔵されています。本作には《ブルターニュの老婦》を含む数多くの習作が残されており、本作にもとづく版画も制作されました。

ブルターニュの婚礼やパルドン祭の縁日など、庶民の生活模様を自然主義的な態度で描いたシモンは、別荘で家族や友人と過ごすひと時も数多く描きとめました。本作は、シモン家の子どもたちが別荘の庭で催した芝居を大人たちが見物する情景を捉えています。赤い天蓋の下で演奏や踊りを披露する子どもたちと、それを暖かい眼差しで見つめる大人たち。両面と平行にそびえる別荘のファサードや生垣は、庭そのものを舞台であるかのように見せる書割りの役目を担い。それが家族の集いの親密な雰囲気を一層強めています。




18歳で法律を学ぶべくパリへ渡った黒田は、日本人画家たちとの交流を経て美術へ転向し、ラファエル・コランに師事します。1891年と翌年の8月から9月にかけては、久米桂一郎とともにブレア島を訪れ、ばら色の花崗岩が連なる海岸風景や住民の子供たちをモデルに作品を手掛けました。こちらを鋭く見つめる「真赤な髪を持った百姓の子供」を描いた本作では、少女のほつれた髪、左右で異なる靴、椅子の上の欠けた椀などから貧しい生活環境が垣間見えます。画面は激しい筆致と鮮烈な色彩で覆われ、強い日差しを浴びた少女の赤毛は黄金色に輝いています。

1886年に渡仏した久米は、同じくコランの門下生である黒田清輝とともに1891年と1892年の秋にブレハ島へと足を運び、制作に励みました。二度目の滞在時に着手されたのち、パリで完成されたと思わしき本作は、《晩秋》とともに久米の留学の集大成というべき大作です。画面では、おそらく滞在先のオテル・サントラルの庭を舞台に、ブルターニュのコワフと木靴を身につけたふたりの少女が林檎を収穫する様子が描かれています。その主題や陽光の表現は、カミーユ・ピサロの作品を想起させるかもしれません。画面の大きさからも、翌年のサロン出品を念頭に制作されたものと考えられます。

国立西洋美術館常備展











本日も最後までご愛読ありがとうございました。











コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 1892 油彩、カンヴァス あわせて読みたい 憧憬の地 ブルターニュ展と国立西洋武術館の須玉の作品紹介 […]